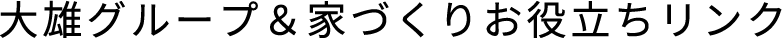~お家の歴史の豆知識 その1~

皆様 こんにちは!!!
岐阜・愛知・三重・滋賀の注文住宅といえば、、、、
YOUHOUSE🏠の藤田です!!
最近は雨が多く降ったり、暑くなったりと気温の上がり下がりが激しく、体調には気を付けていかなくてはなりませんね。。(´;ω;`)
また、コロナも増えてきましたので、今一度対策をして気を付けていきましょう!!

私は、現在建築の知識に関して勉強中ですが、
お家のデザインや性能について興味があり調べていたら、
昔のお家の歴史・性能・デザインで面白いものが見つかったので、紹介致します!
今回は、縄文時代~室町時代 のお家はどのようなものだったのかについて説明させて頂きます!
<縄文・弥生時代 紀元前14000年~3世紀ごろ>
① 日本の家のはじまり

日本の初めてのお家は、『たて穴住居』(半地下式)というものから始まりました。
皆様も小学生の時などに勉強したことあると思いますが、最初のお家です!!
たて穴住居とは、、、現代でいう床がなく、すべてが土間で屋根はアシやカヤを葺いていたらしいです。
また、柱を4本立てる構造として、現在の木造建築とベースは同じになるそうです。
<弥生時代 紀元前4世紀~3世紀ごろ>
②身分の違いで住居が違う時代に

弥生時代には、『高床住居』というものができました。←卑弥呼がいた時代ということもよく耳にしますね👻
高床住居とは、、、軸組構造を採用しており、たて穴住居と異なり、土間を持たず床があります。
(理由として、農作業や調理をしなくてよいため🥬)
また、たて穴住居より、湿度や夏の暑さ対策ができ、快適に暮らせるそうです。ベランダのようなものもあり、寝殿造りのベースにもなったそうです。
<平安時代 794年1185年ごろ>
③貴族の住まいとしてさらに進化

平安時代には、『寝殿造り』というものができました。←身分が貴族・庶民と分かれるようになり格差が生まれ始めました。
寝殿造りとは、、、内部は土間式ではなく板の間!また、柱だけのため、壁はほとんどなく、屏風や布などで仕切り、部屋として使っていたそうです。
庶民の家は、礎石(柱を支える石のこと)の上に柱を置く貴族の家とは違い、地面に穴を掘り固定させていたそうです。
<室町時代 1336年~1573年>
④和室の原型となる住宅が登場

室町時代では、『書院造り』というものができました。←少しずつ現代のお家の形に近づいてきましたね☻
書院造りとは、、、現代の和室の原型であり、全面に畳が敷き詰められ、床の間、障子なども作られるようになりました。
いかがでしたか?縄文時代のお家はデザインや性能に関しては、悩むところがありますが、、、、
時代が変化するとともに、お家の様子は現代に近づいてきましたね♪
次回以降に江戸時代以降のお家について、また紹介致します!!
それでは皆様体調には気を付けてお過ごし下さい☺